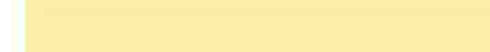
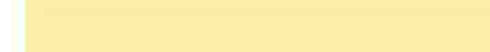
PHP2010年6月号掲載記事


◆◇◆◇ 現場に美神がおわします ◇◆◇◆
「人生で壁にぶつかった経験は?」と聞かれると、
「あら、私は壁画をやっているから、いつも壁にぶつかっているのよ」
なんて冗談を言うんですよ(笑)。
でも、本当。
壁画の制作は、まさにピンチや壁にぶつかることだらけです。
☆ お守り代わりの言葉 ☆
私が最初に壁画を手掛けたのは、今から二十年ちょっと前。
中国・西安のホテルでした。
まだ建築途中の吹きっさらしの中で、幅六十メートルもある大きな壁に絵を描く。
ビルの四階分ほどの高さの足場を組んで、まずは下塗りから始めます。
絵描きといえば、優雅にコーヒー片手に静かな音楽を聞きながら・・・なんていうイメージがあるかもしれませんが、 とんでもない。
制作の場は、まさに、“現場”という雰囲気。
私など、日本から出稼ぎにきた塗装業者さんだと思われていたぐらいです。
西安は砂漠の入り口ですから、夏は四〇度、冬はマイナス十度以下という厳しい気候の土地です。
寒い時はたくさん着込むんですが、体の自由が利かなくなると、思うように筆を動かせないし、
事故につながる可能性もある。
だからあんまり着ぶくれするわけにもいきません。
確かに条件は過酷です。
でも、だからと言って落ち込んだり、「できません」なんて弱音を吐いてはいられない。
そんな時、私を勇気づけてくれたのが、自分の信念である「現場に美神がおわします」という言葉でした。
どんな場所であれ、現場に行けば、そこに必ず美の神様がいて、ケガをしないように、いい作品ができるようにと、
私を助けてくれる。
そう信じることで、力が湧いてくる気がしたんです。
以来、この言葉がお守りのようになりました。
☆ 「これ」と決めつけない生き方 ☆
私の場合、壁画を描く時、あらかじめ紙の上で下絵を描いておくことをしないのですが、それも美の神様を信じているからです。
その空間に身を置いて集中すれば、美の神様は、必ず何かひらめきを与えてくれる。
別のいい方をすれば、頭で考えたイメージより、その場の直感の方が大切ということ。
「こんなはずじゃなかった」なんていう壁にぶつかっても、直感を信じていれば、臨機応変な打開策は見つかると思うんです。
その一つの例が、長野県・蓼科にあるホテルの壁画を頼まれた時のことです。
煙突の内側のような、吹き抜けの大きな壁に絵を描く。
ところが、現場に行ってみたら、その壁の正面に巨大な針が横たわっていて、角度によっては壁が見えなくなって
しまう設計だったんです。

まさに「こんなはずじゃなかった」という事態でした。
でも、その時、美の神さまが、また私を助けてくれた。ひらめいたんです。
「そうか。取れないんなら、逆にそこにも絵を描いてしまえ」と。
結果的には、正面の壁画と梁の絵との相乗効果で、かえって奥行きがあって美しい空間が出来上がった。
マイナスだと思っていたものが、プラスに逆転したんですね。
もしこの時、頭で考えたイメージや、あらかじめ描いた下絵にこだわっていたら、梁の出現という文字通りの壁にぶつかった時、
手も足も出なくなってしまったかもしれない。
要するに、何ごとも「これ」と決めつけないことが大切だと思うんです。
二十代の時、四年間ほどインドで暮らしたことがありました。
街中に人や車、牛や羊があふれかえり、喧騒と混沌うずまく異空間。
最初は足がすくんで一歩も歩けないほどでした。
ああいうところでは、自分が「こうしよう」と決めてもこの通りにできないことばかり。
焦ったって仕方ないし、「私はこうよ」と自分のキャリアを振りかざして気取ったところで通用しない。
一番いい生き方は、「これがダメなら、こうしよう。それもダメなら、またこうしてみよう・・・」と、
その場その場でしなやかに形を変えていくことだったんです。
そんな“アメーバ精神”のようなものを、インドで学んだ気がします。
だから、今、少々の困難にぶつかってもへこたれないんですね。
☆ 喜んでくれる人の笑顔がパワーの源 ☆
西安のホテルの第一作目から始まって、私の壁画は五十三作となりました。
「大変ですね」とよく言われます。
でも、本人はあーら、いつの間にかそんなにって感じ。
鈍いんでしょうか。
それと、やはり私は絵を描くことが好きなんですね。
何もない真っ白な壁から絵が生まれ出てくるあの快感が忘れられない。
何から何まで全部一人でやるのですが、実は、この創作の喜びを他の人にあげたくないからじゃないかと自分で思うほどです。
また、一番大きな力は、私の作品を見て喜んでくださる方々の存在です。
先の蓼科のホテルでは、現場で工事をしていた職人さんの一人が、毎日私の壁画が出来上がる過程を楽しみに
見ていてくださった。
最初、私はそれを知らなかったんです。
ところがある時、描いた人物の一人が構図上必要なくなって、塗りこめて消さざるを得なくなったことがありました。
そうしたら、その職人さんが「あれぇ。ここにいた女人がいなくなっちゃたよ」
と寂しそうに言うんですね。
それで、毎日見ていてくれたことを知ったんです。
「この現場で、この絵を見るのが何よりの励みだった」とおっしゃってくださって、感激しました。
こういう体験の一つひとつが、私を元気にさせてくれるのです。
(C)Noriko Tamura All Rights Reserved